公認会計士はAIに代替されるのか
近年、AI(人工知能)の発展により、多くの業界で業務の自動化が進んでいます。公認会計士の業務も例外ではなく、AIによる代替の可能性が議論されています。
しかし、すべての業務がAIに置き換わるわけではありません。AIの得意分野と公認会計士の専門性を踏まえ、どのような業務が影響を受けるのかを見ていきましょう。
業務の全てをAIに代替させることは難しい
公認会計士の業務全てをAIに代替させるのは難しいとされています。その理由は、AIが得意とする業務範囲と限界にあります。AIは膨大なデータの処理やパターン認識に優れており、効率的なデータ分析や異常検知などで力を発揮します。しかし、AIには創造性や倫理的判断、複雑な意思決定を行う能力が欠けているため、人間が担うべき部分が残ります。
たとえば、企業の財務諸表の分析においてAIは異常値の検出や統計的傾向の特定に役立ちますが、業界特有の事情などの判断をすることは難しいとされています。こうした高度な専門性や多様な状況に対応する柔軟性は、人間にしかできません。
AIに代替される公認会計士の業務
AIによって代替が可能だとされている業務は、以下のような業務です。
- データの整合性チェック(証憑突合、帳簿突合)
- 繰り返し行う定型的な分析業務(分析的手続、勘定分析)
- 予測分析による異常検知
これらの業務は、ルールが明確でデータ処理の手順が標準化されているため、AIが得意とする分野です。AIは膨大なデータを短時間で処理し、正確な結果を導き出すことができます。
AIによる自動化が進むことで、公認会計士の役割も変化しつつあります。定型的な業務の自動化により、会計士はより戦略的な業務に注力することが求められるでしょう。
AIの導入を前向きに捉え、積極的に活用することで、業務の効率化と高度化の両方を実現することが可能になります。
参考:AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響
AIに代替されにくい公認会計士の業務
AIに代替されにくい業務は、以下のような業務です。
- 経営層やクライアントとの交渉
- 監査計画の立案、監査リスクの評価
- イレギュラーな事象の判断(不正リスクへの対応)
これらの業務は、データ分析だけでなく、経営の背景や業界特有の事情を考慮した柔軟な対応が求められます。
特に、不正リスクの判断では、AIでは見抜けない経営層の意図や細かい不正の兆候を把握する力が必要です。また、監査計画の立案では、将来の経済環境を予測し、適切な手続きを設計する判断力が重要です。
AIはデータ処理には優れていますが、人との信頼関係構築や複雑な判断には会計士の経験と洞察が欠かせません。
大手会計事務所によるAI活用事例
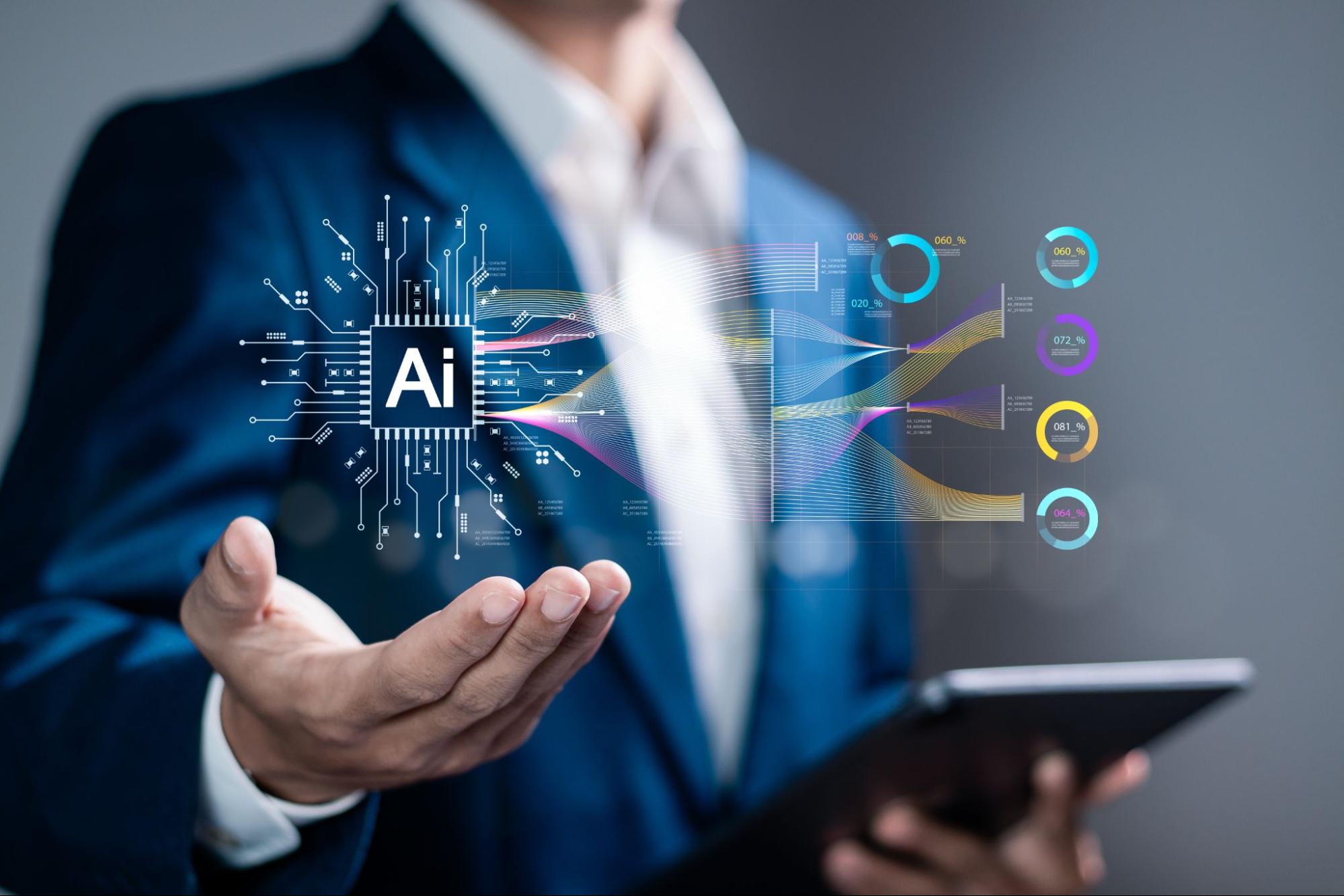
近年、AIの進化に伴い、大手会計事務所では監査業務の精度向上や効率化を目的に、AI技術の積極的な導入が進められています。
AIを活用することで、膨大なデータの処理や不正リスクの検知が可能となり、より高度な監査の実現が期待されています。
ここでは、各大手監査法人におけるAIの活用事例について紹介します。
EY新日本有限責任監査法人
EYでは、企業の財務諸表に対する異常検知を行うために、複数のAI監査ツールを開発・実装しています。主なAI監査ツールは、以下のようなものがあります。
- WebDolphin/TBAD:財務分析AI
- General Ledger Anomaly Detector(GLAD):会計仕訳の異常検知
- Sales Ledger Anomaly Detector(SLAD):売上取引の異常検知
- Project Progress Anomaly Detector(PPAD):プロジェクト進捗の異常予測
EYは、東京大学大学院などの学術機関と連携し、監査業務のさらなる精度向上と効率化を目指しています。AIを活用することで、従来の監査プロセスに比べて迅速かつ正確なデータ分析が可能となり、監査人の判断をサポートします。監査の高度化が求められる現代において、AIの積極的な導入が監査品質の向上に大きく寄与することが期待されています。
有限責任監査法人トーマツ
有限責任監査法人トーマツでは、AIを活用した不正検知モデルを開発し、2022年1月から本格導入を開始、2023年1月に特許を取得しました(特許番号:第7216854号)。このモデルは、財務データを分析し、不正リスクの早期発見と監査業務の効率化を目的としています。主な特徴は以下の通りです。
- 勾配ブースティング技術の活用: 予測精度の向上と不均衡データへの対応を実現
- SHAPによる説明可能なAI(XAI): スコアへの影響要因を可視化し、監査人の理解をサポート
- 不適切事例のレコメンド機能: 過去の不正事例と比較し、リスクの高い取引を特定
この不正検知モデルは、過去の有価証券報告書や訂正報告書のデータを学習し、不正の可能性をスコア化することで、企業の不適切な財務報告を識別します。すでに100社以上の導入実績があり、今後もさらなる適用拡大が予定されています。トーマツは「Audit Innovation®」の取り組みを通じ、AIを活用した監査プロセスの標準化と品質向上を進めています。
有限責任あずさ監査法人
あずさ監査法人では、AI・機械学習を活用した「不正リスク検知SUNモデル」を開発し、2019年8月から法人内での利用を開始しました。このモデルは、財務諸表の不正リスクをスコア化し、適切な監査手続を支援することを目的としています。主な特徴は以下の通りです。
- 不正リスクのスコア化: 財務諸表が不正を含む可能性を数値化し、不正の兆候を早期に検知
- 3つの不正タイプ別サブモデル: 「売上過大計上」「費用過少計上」「資産過大計上」などの不正タイプを分類
- AI・機械学習とプロフェッショナルの協働: AIが監査人の意思決定をサポートし、精度向上を実現
SUNモデルは、過去10年以上の財務データを基にした「Balanced Random Forest」手法を採用し、経年変化や同業他社比較も行うことで、より正確なリスク評価を可能にしています。あずさ監査法人は、今後も監査品質の向上と不正リスクの早期発見を目指し、AI技術の活用を進めています。
PwC Japan有限責任監査法人
PwC Japan有限責任監査法人では、AIを活用した監査リスク管理の強化に取り組んでいます。特に、AI技術を活用することで、監査業務の効率化と監査品質の向上を目指しています。主な取り組みは以下の通りです。
- 監査リスクの可視化: 財務・非財務データを活用し、取引単位(ミクロレベル)および事業拠点単位(マクロレベル)でのリスク評価を実施
- 自然言語処理による経費分析: 立替経費の摘要欄を分析し、異常な取引を自動的に識別
- 異常検知モデルの適用: 仕訳データや購買取引を対象に、AIが異常なパターンを抽出し監査人の判断をサポート
AI活用の主なメリットとして、監査人の工数削減と気づきにくい知見の獲得が挙げられます。ルールベースのアプローチと機械学習の併用により、監査対象のデータ分析を強化し、より精度の高いリスク管理が可能になります。PwC Japan有限責任監査法人は、今後もAI技術を駆使し、監査プロセスの高度化と持続的な信頼性向上を図る方針です。
参考:AIを活用した監査リスク管理の事例 | PwC Japanグループ
公認会計士の業務がAIに代替されない理由
AIの進化により、公認会計士の業務の一部が自動化される一方で、すべての業務がAIに置き換わるわけではありません。
会計業務には、専門的な判断やクライアントとの信頼関係構築など、人間ならではのスキルが不可欠です。
ここでは、公認会計士の業務がAIに代替されにくい理由について詳しく解説します。
会計処理の選択には判断が必要になるため
会計基準の適用や複雑な会計処理においては、企業のビジネスモデルや市場環境に応じた柔軟な判断が求められます。
例えば、減価償却の方法の選定や収益認識基準の適用は、企業ごとの経営方針や法規制の変化を踏まえた上で判断する必要があります。
AIはデータ処理のスピードや精度には優れていますが、会計処理の適用における微妙なニュアンスや企業の特殊性を考慮した意思決定には限界があります。そのため、公認会計士の専門的な知識と経験に基づく判断が不可欠です。
セキュリティ対策のため
財務データは機密性が高く、不正アクセスやデータ漏洩のリスクが常に存在します。AIを活用することで業務の効率化が進む一方で、システムへの過度な依存は、セキュリティ面での脆弱性を生む可能性があります。
また、企業のガバナンス体制の強化や、不正防止策の策定においても、AI任せにするのではなく、公認会計士が果たすべき役割が重要となります。
顧客との信頼関係の構築が必須なため
公認会計士の業務は、単なる数値のチェックにとどまらず、経営者やステークホルダーとの信頼関係を築くことが重要です。
例えば、監査業務においては、財務データの正確性だけでなく、クライアントの事業戦略や課題を理解し、適切なアドバイスを行うことが求められます。
AIはデータに基づいた客観的な評価はできますが、クライアントとのコミュニケーションや、経営方針に即した対応を柔軟に行うのは人間の役割です。
このように、状況に応じた対応力や、長期的な関係構築のための対話力が公認会計士には不可欠です。
公認会計士の活動領域が多様なため
公認会計士の業務は、監査だけでなく、税務、コンサルティング、M&A支援、内部統制評価など幅広い分野に及びます。また、監査法人での経験を活かし、企業のCFOや経営コンサルタント、さらには独立開業など、多様なキャリアパスが存在します。多くの業界や市場で会計士の専門知識が求められており、企業の経営戦略に深く関与する役割も担っています。
公認会計士のキャリアについては、以下の記事を参考にしてください。
『公認会計士のキャリアパス|キャリアアップに必要なスキルや成功のコツ』
AIが一部の業務を支援することはできますが、多様なフィールドでの活躍が求められる公認会計士の役割は今後も重要であり続けるでしょう。
このように、公認会計士の業務はAIの進化によって補完される部分があるものの、最終的な意思決定、倫理観、信頼関係の構築といった側面では人間の役割が不可欠です。
公認会計士は今後AIにどう向き合うべきか

AI技術の発展により、公認会計士の業務にも変化が求められています。
ここでは、AIと共存しながらキャリアを築くために必要なポイントについて解説します。
AIを活用するスキルが必要になる
公認会計士には、AIを活用する基本的なスキルが必要です。すべての会計士がAIの専門家になる必要はありませんが、AIがどのようにデータを処理し、監査業務に貢献できるのかを理解することが重要です。例えば、AIが財務データを自動分析し、異常値を検出する仕組みを把握し、適切に活用することで、より迅速かつ正確な監査が可能になります。AIの導入により、定型的な業務の効率化が進む一方で、会計士は高度な分析や戦略的判断に時間を割くことが求められます。
判断力が必要になる
AIの導入が進む中でも、公認会計士の「判断力」の重要性は変わりません。AIが提供する分析結果を適切に評価し、経営者やステークホルダーに対して説明責任を果たす必要があります。日本公認会計士協会の報告書によると、「AIに代替した業務をどのように判断するか」というスキルが監査責任者に問われることが予測されています。
AIは膨大なデータを処理し、一定のパターンを示すことはできますが、その判断の正当性や監査の信頼性を確保するためには、会計士の専門知識と経験が不可欠です。今後は、AIを適切に活用しながらも、人間の判断をどのように組み合わせるかが重要なスキルとなります。
コミュニケーション能力が必要になる
AIでは代替できない「コミュニケーション能力」は、今後の公認会計士にとってさらに重要になります。監査や財務アドバイザリー業務では、経営層やクライアントとの対話を通じて、問題の本質を理解し、適切な提案を行うことが求められます。AIがデータ分析を自動化することで、会計士はより戦略的なコンサルティングやクライアントとの信頼関係構築に時間を割くことが可能になります。顧客のニーズに寄り添い、柔軟に対応する能力が、AI時代の公認会計士の差別化要因となるでしょう。
AIの活用が進む中で、公認会計士には新たなスキルが求められる一方で、従来の専門知識や倫理観、対人スキルが今後も重要な役割を果たします。AIを最大限に活用しながらも、人間ならではの強みを活かして、より高度な監査業務を提供していくことが期待されています。
ITやAIに関心がある公認会計士の方におすすめの求人
ここでは、ITやAIに関心がある公認会計士の方におすすめの求人を紹介いたします。
会計とITを融合させたコンサルティング会社
| 業務内容 | 経営/会計分野のコンサルティング業務(経営管理、財務・管理会計、原価計算・管理、連結決算・管理システムの構想策定やシステム導入、IFRSコンサルティング、内部統制支援、システム監査、電子帳簿導入支援コンサルティング、株式上場・M&Aコンサルティングなど) |
| 必要な経験・スキル | ・公認会計士(監査法人出身者)・会計システムへ関心がある方 |
| 想定年収 | 年収500万円~900万円 (経験・能力により応相談) |
公認会計士の転職・キャリアアップならVRPパートナーズへ
VRPパートナーズは、公認会計士の資格を持つ方に特化した転職エージェントです。監査法人から事業会社、FAS(Financial Advisory Services)、コンサルティングファームなどへの転職をサポートし、キャリアアップを目指す方に最適な選択肢をご提案します。
監査法人からの転職実績多数
当社は、大手監査法人や中小監査法人への転職を含め、監査法人からの転職はもちろん、監査法人への転職においても豊富な実績があります。監査法人ならではの経験を最大限に活かし、監査法人でのアドバイザリー部門への転職、FAS会社への転職など、多彩なキャリアパスの実現をサポートします。
転職した後のキャリアも考え併走いたします
転職はゴールではなく、あくまで新たなキャリアのスタートです。
VRPパートナーズでは、ご希望のキャリアプランを丁寧にヒアリングし、長期的な成長を見据えたサポートを提供します。転職後のスキルアップやキャリア形成に関するアドバイスも行いますので、安心してご相談ください。
相談料・仲介料はいただきません
転職活動において、費用面のご心配は不要です。VRPパートナーズでは、登録から転職成功まで一切の相談料・仲介料をいただきません。無料で質の高い転職サポートを受けられるため、安心して転職活動を進めていただけます。
まとめ
AIの進化により、公認会計士の業務の一部は自動化が進むものの、すべての業務がAIに代替されるわけではありません。特に、経営層との交渉や監査リスクの評価など、人間の判断力やコミュニケーション能力が必要な業務は、会計士の重要な役割として残ります。
AIを活用することで、業務の効率化と高度化を両立させることが可能です。今後は、AIを使いこなすスキルや、専門的な判断力、顧客との信頼関係を築く力が求められます。
VRPパートナーズでは、公認会計士のキャリアアップを支援し、転職後のサポートも一貫して行います。転職をご希望の方は、ぜひ一度VRPパートナーズにご相談ください。


















