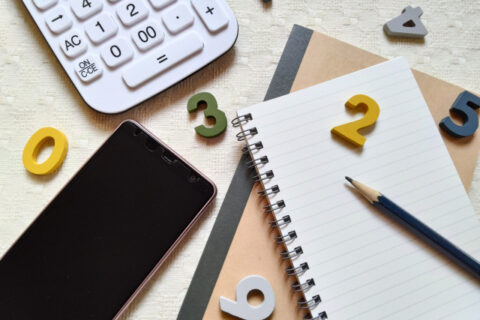2025年は令和7年ですが、昭和100年という節目の年でもあります。
先日、何気なく『年間カレンダー』に目をやると、3月25日が火曜日であることに気づいたのですが、筆者にとって人生初となる「大阪勤務」がスタートした1997年と奇しくも同じカレンダーであることに気がつきました!
そこで今回のコラムでは、30年近く前の記憶を頼りにしながら、当時の“古き良き”思い出をご紹介いたしましょう。(←記憶違いの点があれば、何卒ご容赦願います。)
1.25日始まり
アクチュアリー試験のうち第2次試験(専門科目)の1つである「保険2(生命保険)」の教科書『第1章 生命保険会計』13ページ上から2~3行目に、“保険会社の成績月と歴月が異なる場合”という記述があります。
実は、筆者が社会人デビューした保険会社では、成績月が「25日始まり」となっており、「成績月」に留まらず、人事異動などの社内スケジュールについても、この「25日始まり」で運営されていました。
1997年3月25日(火)から大阪勤務となりましたが、東京からの移動ということもあり、上司の計らいで前日の24日(月)に有給休暇をいただくことができ、直前の土日を含む3日間で無事に引っ越し作業を完了できました。
なお、“借上げ社宅”を求めて不動産会社を訪問した際、“日割り家賃が発生”と言われ、“何故、大手金融機関が4月1日始まりではないの?”と聞かれてしまい、回答に窮した記憶があります。
2.生命保険必携一九九六
財経詳報社といえば、主務官庁を含めた行政組織関係の出版社として有名ですが、上述の“大阪転勤”で決算部門に配属されたため、上司に挨拶した際、同社刊行の『生命保険必携一九九六』という小冊子を(自腹で!)購入せよとの業務命令をいただけました。
早速、阪急梅田駅近くの「旭屋書店」で当該冊子を購入して会社に持参したのですが、幸い、平成6年(1994年)の入社研修時に会社から『生命保険必携一九九四』が配布されましたので、馴染み深い書籍として、今でも自宅書棚の両隣に鎮座しております!
なお、当時は、当該冊子が毎年発行されているものと勘違いし、血眼になりながら『生命保険必携一九九五』を探し回った苦い記憶(笑)がありましたが、振り返ってみれば、これを機に、例えば、『保険業法コンメンタール』などの書籍にも辿り着けるなど、その後の長い保険会社人生にとって大変有意義な機会となりました。
また、業界の懇親会で、他社のアクチュアリーから、「財経詳報社の刊行物は保険会社実務にとっては有難いが、一部の全国紙では、“免許事業者に主務官庁が発行する書籍を有償で配布することは『小遣い稼ぎ』でありケシカラン”と批判的な記事が出た」とのコメントがとても印象的でした。
3.営業研修
いわゆる「アクチュアリー採用」だったので、支社や営業部などで営業の仕事をする機会は決して多くなかったのですが、昇格・昇給のため、総合職全員に営業研修を3か月間実施することが、当時は義務付けられていました。
某拠点で研修活動をしていた際、支社に所属する先輩から、
1)大阪城を起点として、1丁目、2丁目etc.
2)大通りを挟んだ向かい合わせが同じ町名
といった、営業活動のコツ(=住所表示)を教えていただけたことも貴重な経験でした。
残念ながら、当該研修は既に廃止された模様ですが、保険会社の総合職としては、当然、営業職員や保険代理店の方々がどういう思いで日々お客様と接しているのかを、身をもって知ることは決して無駄ではないようにも思うのですが、まあ、これも時代の流れでしょう。
4.保険会社の破綻
1997年4月の日経新聞一面に、日産生命に業務停止命令という趣旨の記事が出ました。
筆者は京阪電車沿線に居を構えて、淀屋橋まで小一時間かかる通勤経路でしたが、電車内で偶々隣人が読んでいる朝刊を横目で見ながら、“生命保険協会データを朝一で整理せねば!”と意気込んで出社したのですが、案の定、既に優秀な上司が9時前にデータ整備を完了し、主計部長(アクチュアリー!)に報告済みでした。
今思えば、4~5月の決算期には、最低でも8時までには出社していたようでして、上司のやさしさから“お前は異動したばかりで新婚だから9時出社でいいよ”と仰ってくれた上司には、改めて深い感銘を抱いております!
なお、勤務先は、歴史上の人物である織田信長をCMに起用して、その画像などから地声を再現した「保険を統一じゃ!」というフレーズで一世風靡した感もありましたが、後述する“カレー事件”など、20世紀の犯罪史に残る凶悪犯に遭遇するとは夢にも思わない平和な時期を過ごせた貴重な年でもありましたが。
5.社長交代
1997年4月に勤務先の社長が交代したのですが、当時の会長(=全社長)が、いわゆる財界活動に関心が高かったのに対して、新社長はそれほど関心はなく、むしろ本業に専念する姿勢であったことを、勤務先を退社した後に知りました。
実際、新旧社長同士は人事部の上司部下(部長&課長)の関係であったようでして、某週刊経済誌でもお二人の特異なご関係が小説家されるなど、なかなか興味深いイベントもあるような噂も絶えませんでしたが。
なお、未だに人事部門出身者を中心とする社長系列に違和感を抱く著名な大学教授も多くいらっしゃるように感じます。
ちなみに、昨年末の週刊誌報道で露呈した「フジTV問題」でCM出稿取下げの動きが相次いだことの発端も、次期経団連会長が保険会社ご出身であったため、当該取下げの動きが加速したとの報道も記憶に新しいところかもしれません。
6.百周年記念大会
1899年に設立された日本アクチュアリー会は、1999年に百周年を迎えることができ、新宿の京王プラザホテルにて、同会百周年記念大会が盛大に開催されました!
筆者は大阪勤務最後の年でしたが、残念ながら準会員であったため、開会式などの主要イベントに参加できなかったものの、大会部会委員として、様々な“裏方作業”に従事できたことが大変貴重な機会となりました。
その後、ケーブルテレビで必殺仕事人や太陽にほえろなどの昭和のテレビ番組に触れる機会をいただけた際、故・沖雅也氏だ当該ホテルの屋上から飛び降りられたことを知り、心が痛むと共に、百周年記念大会が改めて蘇ってきました。合掌。
7.メガバンク不祥事
大昔、ダウンタウンのトーク番組(例.ダウンタウン也etc.)で、高校の先輩でもある『故・伊丹十三氏』を交えた回で、“伊丹と十三はどちらも関西の有名な駅名だ!今風に言えば、『西中島・南方』と言っても過言ではない!!”と松本人志氏が番組内でコメントされ、個人的に大笑いした心地よき記憶があります。
偶々、大学生時代に阪急宝塚線沿いに下宿していたこともあり、「十三駅」を(ジュウゾウではなく)ジュウソウとすらすた読めたのですが、その「十三駅」のホーム反対側で大勢の第一勧業銀行行員の方々が“ばつが悪そうに”首を垂れていた御姿がとても印象的でした。
当時の“大蔵省”を含む“ノー●ンしゃ●しゃ●事件”は、永遠に語り継がれる汚点として語り継がれるかもしれませんね。
いかがでしたか。幼少の頃、同級生が共通の知人から休み時間に「何年何月何日は何曜日?」というクイズを即答し大変驚いた記憶があります。当人曰く、「365≡1(mod7)」&「4年に1度の閏年」という2つのルールの組合わで、『28年周期(=7×4)』、即ち『28年経過すればカレンダーが元に戻る』ということを頭に叩き込んでいたことで即答できたという裏技を教えていただけました。人生100年時代と言われて久しいですが、同じカレンダーを過ごせる年も高々3回程度しかないことを改めて認識すれば、少し寂しい感じが禁じ得ません。
(ペンネーム:活用算方)
2025年04月28日 (月)
28年周期(1997年の思い出)